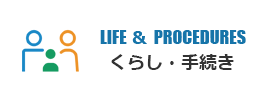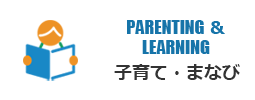本文
「移住風景 令和7年5月号」の掲載について
「移住風景~八頭町地域おこし協力隊活動の現場から~令和7年5月号」を掲載しました。
県外へ広がる活動(小宮春平)
この2年間、様々なため池の管理に関わらせていただき、農業用ため池の水の抜き方や樋管(ひかん)の管理方法など、多くのことを学ばせていただきました。また、そういった活動の中で特定外来生物のウシガエルやブルーギルなどの駆除も行わせていただき、いくつかの池では劇的に数を抑え込むことに成功しています。
そういった八頭町の活動は、実は環境分野では注目されつつあり、この度、長野県安曇野市でのウシガエル駆除のアドバイス・現地指導に招聘していただきました。市から委託を受けた生物保全団体「わかぜん」と連帯し、水位管理や樋管の復旧作業を進め、この冬中にはこの池の外来種をほぼ根絶するに至りました。鳥取県で培った保全のノウハウが、こうやって他県で活用されるのは良い流れです。
また、夜間などの現地指導以外の時間は、山間地のため池や明渠排水(めいきょはいすい)を案内していただき、サンショウウオやアカガエルの産卵地を案内していただきました。水辺と山との接続など、勉強になるところが多く、これらの知見はしっかり持ち帰り、反映させていきたいところです。
東西交流を加速させて、鳥取を環境の先進地域として勇名を馳せる時を目指し、今後も頑張っていきます。
(写真1)ため池の現地指導

(写真2)夜の水路観察会

梨も急な寒さは嫌い?(渡辺彌龍)
春が近づいて来るにつれ、梨の木たちも休眠期を終え、蕾を開かせてきています。
まだ経験が浅いので休眠中の寒さが木たちに十分だったのかは分かりませんが、十分に寒さを経験しないと梨の実も良いものにならないそうです。
とは言え花が開き始める今の時期に急激な寒さを経験することも良くないようです。寒さが受粉に影響を及ぼしたり、奇形の実になってしまったりすることもあるので天気予報の気温とは常ににらめっこしなければなりません。
地域の果樹農家さんとの交流の機会も増え、剪定作業を手伝わせていただく機会も増えて来ました。剪定をしっかりしなければ新しい新梢(しんしょう)も出てこず、枝が厚ければ日当たりも悪くなり日陰にある短果枝(たんかし)も元気がなくなり枯れてしまったりするようです。
自分が就農をした後も、この春に学んだ経験・ノウハウを意識した剪定をしたいと思いました。
(写真1) 寒さの残る樹園地
(写真2)枝越しの夕陽

(写真3)寒さもどこ吹く風な我が家の猫

居場所づくりに必要なこと(杉川藍月)
3月、岡山県美作市を訪問し、人おこしシェアハウスを運営しているNPO法人「里山エンタープライズ」へ視察に伺いました。
同法人は、ひきこもりや生きづらさを抱える若者世代にシェアハウスの場を提供することで変化のきっかけづくりをしています。福祉施設の形態ではなく、あくまで一般的なシェアハウスの形態をとることで個人の自立や主体性、「生きるって楽しいことなんだ」と再実感してもらうことを心掛けておられました。田舎が持つ穏やかな環境や温かい人々、都会では経験することのできない様々な体験を通して、心と体のリズムが少しずつ、そして自然と整っていく場となっていました。
私は「居場所づくり」の大切さを何度も移住風景に記載してきましたが、八頭にもこういった居場所になりうる拠点が必要であると今回の出張を通してより強く感じました。母親の1人として子育てサークルの代表をしていますが、町内で日曜日に遊べる屋内施設や集まれる場が見付からないのが八頭町の現状であると感じます。若者が気軽に足を運べる活気ある町を作るには、土曜日日曜日も気軽に利用できる拠点づくりがこれからの課題となるだろうと感じました。
(写真1)子育てサークル「ぱくぱく」の様子1

(写真2)子育てサークル「ぱくぱく」の様子2

自然(岡田悠作)
3月、小雨が降る中りんごの木の剪定をしました。雪はすっかり溶けていましたが、空気はまだ凍えるほど冷たく、冬の名残を感じました。
「今年は大雪が続いたから、たくさん枝が折れてるよ」と先輩方。いざ果樹園に入ると、大きな枝があちこちで折れ、その数は5本10本どころではありません。遠くから見てもその被害の大きさが分かりました。
「これは大変だ…」と苦笑いしながら枝を運び、折れた枝が繋がっているところはノコギリで切り落とすといった作業をしました。
切り口からは、拳がすっぽり入るような大きな穴が現れました。自然の力の大きさに圧倒されながら、改めてりんごの木を育てる大変さを実感しました。
(写真1)折れたりんごの木の枝
担当課より
桜も散り、暦の上では立夏を迎えつつあります。周りの山々も新緑が映える中で、八頭町地域おこし協力隊では新たなメンバーを迎えます。隊員の紹介は次号となりますが、協力隊、そして八頭町にもフレッシュな風を吹き込んでいただければと思っております。(田渕)