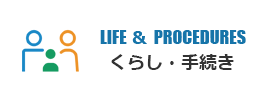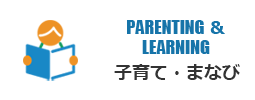本文
「移住風景 令和7年3月号」の掲載について
「移住風景~八頭町地域おこし協力隊活動の現場から~令和7年3月号」を掲載しました。
農作業中の事故に注意(渡辺彌龍)
1月なのに農作業をしていると暑いと感じる今日この頃。八頭町トレーニングファームの研修では剪定作業を勉強しています。今までの研修に比べ難易度も一段と高く感じます。知識、経験、センスの問われる作業ですが、ノコギリとハサミを使う作業なので先ずは焦らず、ケガをしないよう安全に作業していきたいと思います。
先生と作業をしていると、電動バサミを使用している場面に遭遇します。普通のハサミより疲労を軽減できるのだとか。ですが基礎を学ぶ私には、まだ早いということで手動のハサミを使用しています。実際に令和6年には電動バサミで農作業中にケガをされた方もいらっしゃるようです。
農作業での死亡事故は建設業を抜き1番のようです。中でも乗用型農業機械では重大な事故に繋がっているようでした。平成25年350人、令和4年では238人と死亡事故件数自体は減少してるように見えますが就農人口当たりでは増加しています。
私の考える原因の1つとして、「声掛け」があります。建設業などは朝礼で安全に作業できるような声掛けや、別の現場での事故原因などを共有していると聞きます。しかし農業だと、なかなかそういう場面が無いかもしれません。ご家族で農業に携われている方は家庭内で声掛けなどをしてみるのもいいかもしれません。
「今日も1日ご安全に!」
(写真1)剪定作業の様子

冬の両生類(小宮春平)
雪が降ったり止んだり、暖冬なのか厳冬なのかよく分からない今年の冬。それでも生き物たちの生活史は続いています。
12月辺りから、少し水深のある流れの緩やかな山沿いの水路には、サンショウウオやアカガエルたちが降りてきます。気温よりも水温の方が安定していますから、温度変化が厳しい冬には、こういった水中で冬を越します。
2月後半や3月頃、少し暖かくなったら産卵を始めます。チューブ状の卵塊はサンショウウオ、丸くまとまった感じの卵はアカガエル。1mほどあるんじゃないかと言うくらいの細長いものはヒキガエル。時には何十匹ものカエルが集まって、ガマ合戦と呼ばれる様子を見ることもできます。
八頭町ではしばしば見かける生き物たちですが、全国的にはかなり数を減らしている生き物たち。もしも、井手唆いや泥上げの時に見かけたら水路の中に戻してあげてくれたら助かります。ほんのわずかな心配りで、希少な両生類たちとの共存も目指していくことができます。
(写真1)絶滅危惧種のサンインサンショウウオ

(写真2)卵塊とニホンアカガエル

地域の皆さんと作ったお赤飯(杉川藍月)
今年は雪もなく暖かい日の続くお正月でした。そんなお正月明けの3連休にとんどさんがあったのですが、その日に合わせて老人会の皆さんと一緒にお赤飯を作りました。
地域行事が少なくなっていく中、既にある行事に合わせてちょっとした楽しみがあれば良いのではないかという思いつきで始まったのですが、想いを聞いた老人会の皆さんが快く集まってくださいました。
当日は10名の皆さんにご協力いただき、朝から約40個の赤飯おにぎりを作り、地区の方に配ることができました。各自が助け合いながらおにぎりを握った時間は本当に楽しかったです。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
私は初めて八頭町へ訪れたときから自分の中で、「居場所づくり」をテーマに活動しています。昨今、子どもも大人も高齢な方も「自分を必要としてくれる場所」「自分が自分でいられる場所」が見つからず、悩んでしまったり、引きこもりがちになったり、逆に暴力的になってしまう等、「居場所」由来の問題が多くあるように感じます。
八頭町ではまちづくり委員会や社会福祉協議会、子育て支援センター、児童館、地域行事等孤立させない仕組みが多数ありますが、そのちょっとした隙間に私の活動も活かされていけば嬉しく思います。
(写真1)赤飯作りの様子

(写真2)協力してくださった地区の皆さん

りんもんびょう?(岡田悠作)
1月からりんごの樹の剪定に参加しています。剪定をしていると改めて冬が来たなと実感しています。
この剪定は今年のりんごの出来がきまる大事な作業です。枝の伸びる方向や葉っぱの量はどれくらいつくか、どのあたりに何個実ができるかなど考えながら作業しています。
今年はぶくぶくと膨れたイボ状の模様が枝の皮に現れる「輪紋病」という菌が原因の病気が発生しています。梨や桃、トマトにも発生するそうです。
毎年切った枝はチップにして木の肥料にしていましたが、輪紋病がある枝を使用するとまた感染することがあるそうです。この菌があると果実や葉っぱが痛む原因となるので見落とさないように気をつけて剪定をしています。
木は喋れないのでなにも教えてくれませんが見落としたり大丈夫だろうと思ったりしていると大きな病気に繋がります。まだまだ全然わからないことが多いですがもっと注意深く見ていきたいと思いました。
(写真1)輪紋病の枝

担当課より
令和7年も早いもので3月、年度末を迎えます。隊員の中には年度末で卒業という方もいます。八頭町では協力隊事業において定住いただくことを重視し活動を支援しています。卒業後も「町民と役場」のような形で、八頭町を盛り上げていくことができれば幸いです(田渕)
協力隊からのお知らせ
インスタグラム@yazu_life<外部リンク>で八頭の魅力を発信しています!