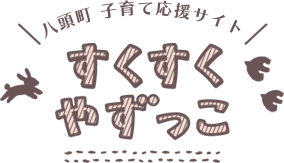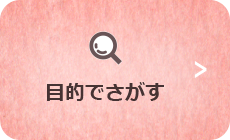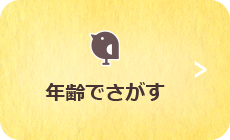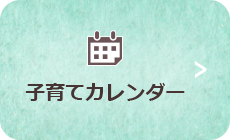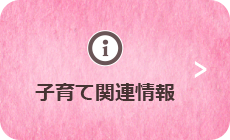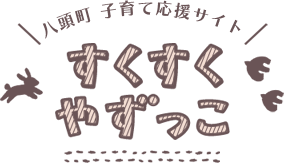本文
児童手当
児童を養育している家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
| こんなとき | 内容 | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 児童手当 |
高校生年代まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。 ※公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。 |
|
窓口のご案内
〈令和6年10月支給分~〉児童手当の制度が一部変更になりました
→詳しくは、児童手当制度の一部変更に関するお知らせ
児童手当について
1.支給金額
| 対象児童 | 第1子・第2子 | 第3子 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
|
3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代修了)まで |
10,000円 | 30,000円 |
※ 18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さまについて、親等の経済的負担がある場合は、第1子としてカウントできます。
[例] 21歳・19歳・15歳 → 15歳の子どもは第3子となり、月額30,000円
23歳・19歳・15歳 → 23歳の子どもは数えません。15歳の子どもは第2子となり、月額10,000円
2.支給日
原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日にそれぞれの前月分までの2か月分手当を支給します。
- 2月支給(前年12月から1月の2か月分)
- 4月支給(2月から3月の2か月分)
- 6月支給(4月から5月の2か月分)
- 8月支給(6月から7月の2か月分)
- 10月支給(8月から9月の2か月分)
- 12月支給(10月月から11月の2か月分)
※ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※「支払通知書」の送付はありませんので、支給日以降に通帳記帳等により登録口座をご確認ください。
3.所得制限
令和6年10月から撤廃され、所得の額に関わらず児童手当が支給されます。
4.現況届
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が八頭町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、八頭町から提出の案内があった方
5.受給対象者
児童の国内居住要件
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
同居優先
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
父母指定者
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
未成年後見人
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
児童福祉施設等への支給
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設や里親などに支給します。
6.申請手続き等
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は、勤務先への申請が必要です。)
認定を受ければ、原則として、申請月の翌月分の児童手当から支給します。申請が遅れると手当を受け取れない期間が発生する場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請月の翌月分からの支給(4月に申請した場合、5月分からの支給)となりますが、出生日や転入日(「異動日」)が月末に近い場合、申請日が翌月にずれこんでも、異動日の翌日から15日以内に申請があれば、申請月分から支給します。(申請が5月になっても、5月分から支給)
異動日の翌日から15日を経過すると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
(参考)児童手当の各種手続き
児童手当の受給要件等に変更があった場合は、次の申請が必要になります。
※公務員の場合は勤務先へ申請してください。
| 事例(一部) | 手続き |
|---|---|
| 子どもが生まれたとき | 認定請求書(既に児童手当てを受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。 |
| 子どもを新たに養育することになったとき | 認定請求書(既に児童手当てを受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。 |
| 他の市町村に転居したとき | 転居前の市町村で受給事由消滅届を提出するとともに、転居後の市町村で認定請求書の提出が必要です。 |
| 児童手当の額が減額されるとき (施設入所等により、児童手当の支給対象となる児童が減ったとき) |
額改定届の提出が必要です。 |
| 児童を養育しなくなったとき (施設入所等により、児童手当の支給対象となる児童がいなくなったとき) |
受給事由消滅届の提出が必要です。 |
| 児童手当の受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先で認定請求書の提出が必要です。 |
| 公務員を退職し、民間の会社等に就職したとき | 認定請求書の提出が必要です。 |
| 所得上限限度額を上回って児童手当等が支給されなくなったあと、所得上限限度額を下回ったとき | 認定請求書の提出が必要です。 |
その他、以下の変更事項があった方はすみやかに届出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金→国民年金)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき