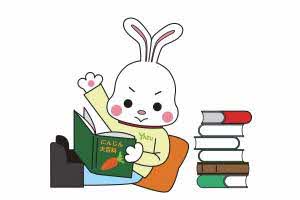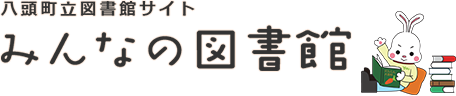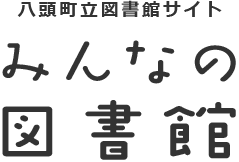本文
くつろぎタイム2025年11月号を発行しました
くつろぎタイム2025年11月号 [PDFファイル/233KB]
あなたの知らない 野生動物の世界
コウノトリやオオサンショウウオ、サルなど、八頭町には様々な種類の野生動物が生息しています。天然記念物として保護されるものがいる一方で、田んぼや畑の作物を荒らす少し困った存在もいます。人間と野生動物が共生するためには、何が必要なのか。まずは、彼らがどんな生活をしているかを知るところから始めてみましょう。
『僕には鳥の言葉がわかる』
鈴木俊貴 著 小学館
言葉を使って会話するのは、人間だけではありません。動物言語学者の鈴木さんによると、シジュウカラは餌を見つけると、特定の鳴き声で仲間に「集まれ!」と呼びかけているそうです。さらに、違う種類の鳥とも意思疎通をすることができ、簡単な2語文もしゃべっているらしい。これは、様々なパターンで実験、観察を繰り返してみたことで分かりました。
鳥たちの豊かな言葉の世界を、ちょっとのぞいてみませんか?
『クマはなぜ人里に出てきたのか』
永幡嘉之 文・写真 旬報社
今年は北海道や東北地方でクマによる被害が相次いでおり、心配になっている方も多いはずです。住宅地に現れるクマを「アーバンベア」と呼ぶ報道も増えています。
長年クマの取材を続けてきた著者は、この言葉は誤解を与える可能性があると指摘します。クマは急に人に慣れたのでも、頭数が増えたわけでもないそうです。クマの行動が変化した原因は、人間の生活様式が変化したことに対応した結果であると説明しています。
『動物行動学者、モモンガに怒られる』
小林朋道 著 山と渓谷社
野生動物の保護といえば、公立鳥取環境大学学長の小林先生が全国的に有名です。芦津の森でモモンガを観察し、車にひかれたタヌキを保護し、日々野生動物と関わっておられます。
多くの人に動物保護や環境保全に関心を持ってもらうには、自分の活動が何らかの利益につながるようなモデルを提示するのが有効だそうです。モモンガのグッズ販売や、ボランティアがガイドする「森のエコツアー」等がその一例。自然を守りながら、地域住民が参加できるビジネスモデルが、今注目されています。
『いきもの六法 改訂版』
中島慶二・益子知樹 監修 山と渓谷社いきもの部 編 山と渓谷社
豊かな自然に恵まれた八頭町ですが、野生の生き物を家で飼っても大丈夫なのか、気になったことはありませんか?
この本によると、オオサンショウウオやコウノトリに触るのは「文化財保護法」で禁止。アメリカザリガニやウシガエルを、生きたまま別の場所に移動させるのは「外来生物法」で禁止。子どもが採ってきたザリガニを「うちでは飼えないから、裏の川に逃がしてきなさい」というのは、実はダメなんですよ!